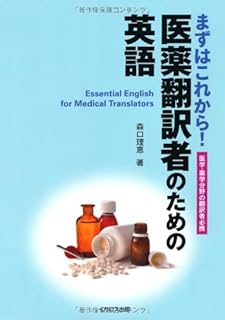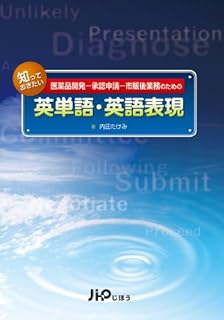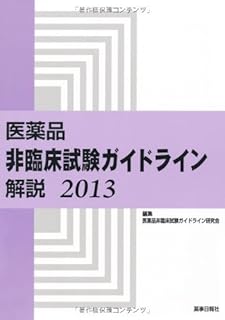ヨシダヒロコです。
11月から治験(臨床)分野その他のトライアル受けていて、治験ではやっと初めて受かったので、参考までに最後のトライアルで参照した本を出します。受かったのは文章の性質上、ひな形になるものが見つかったのが功を奏したのかもしれません。
前から言っていることですが、繰り返しておきます。わたしは20代終わり、およそ20年前から翻訳しないまでも翻訳業界を見ていて、10年ほど前から「治験(医薬)翻訳は文系で知識ゼロでもできます」と翻訳学校があっさり言うようになるのを見てました。その前はそういうことは言われなかったので、需要が増えたか何かしたのだと思います。
治験翻訳には「型」があるとよく言われますが、逆に言うと、基礎知識がなくてもできるということですか?と疑問に思っています。
医学なら生物、薬学絡むなら化学、医療機器なら物理も分かったほうがいい。生物・バイオはわたしは自分で勉強しました。理数科でないと理科3科目は高校の時取れなかったからです。大学の時も生化学は授業あったけど肝心の生物が抜けていたので、最近まで分からないことだらけ。今は学生になって生物や物理を主に勉強していますが、「キリがない」の一言です。
もちろん苦手な分野の文章が来ることもあると思いますが、易しいところから基本的なことも勉強しませんか。化学に関して易しい文章(『五感で感じる~』)を書いているのはその目的もあります。翻訳学校の言うことを甘く見過ぎずに、きちんと勉強しましょう。もうちゃんと考えて勉強している人には要らぬ心配ですけど。